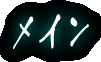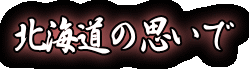
投稿者:BMWさん
何度、この話を文章にしようと思ったことでしょう。
今回この昔話を最期まで書くことが出来たならば、
「もう話しても、いいよ」という許可がおりたということなんでしょう。
彼らからの・・・。
もう、10年が経とうとしています。
当時私は北海道の大学に通っており、同大学の剣道部に所属していました。
ある日の午後、妹の様に可愛がっていたS子という後輩から
食事兼ドライブの誘いを受けました。
その日はコレといった用事も無く、私はいつもの調子でOKし、
彼女の自宅へと迎えに行きました。
普段通りのたわいもない会話をしながらの食事を済ませた後、
S子は希望のドライブのコースの話を始めました。
「ねぇ、今日はさぁ、おにいちゃんの四駆で山道に連れって行って欲しいなぁ」
「林道とかかい?まだ5月だから封鎖してるんじゃないかなぁ、
北海道って雪が残ってる時期が長いからなぁ」
「でしょ、だからこそ、行ってみたいんじゃない!」
「んじゃあ、行ってみるか、でも軽いコースでな、」
私達は暮春の北の林道を目指して、店を後にしました。
まだ四駆ブームなどが到来する以前の話です。
当時は各山々の林道はマナーさえ守っていれば、
一般人でも自由に走ることが出来ました。
しかも盆地である北海道の某市街地からは林道へは
簡単な行程で入れました。
しかし、その年は雪解けが遅かったらしく、
殆どの林道の入り口には封鎖チェーンが張られていて、
その日の林道ツーリングは中止しざるを得ませんでした。
「あああ~、折角楽しみにしてたのになぁ」
S子はワザと不満そうに助手席から声を発しました。
「おいおい、仕方ねえだろ、まぁ、又連れて来てやるよ」
私は子供をあやすような口調で彼女をなだめました。
「じゃあさぁ、中国人墓地に行こうよ!」
「あ?」
今度は私がその地名を聞いて不機嫌に返事をしました。
中国人墓地とは、当時TV、ラジオや雑誌などで話題になっていた
有名心霊スポットだったのです。
「おいおいS子、まさか忘れてんじゃねえだろうなぁ」
「ちゃあんと覚えてますよぉ、おにいちゃん、見ちゃうってヤツでしょ」
「だったら、何で」
私は昔からそんなに強い方では無いながらも、
霊感といわれるモノがあるらしく、
何かしらのタイミングで、幽霊などの類が見えたり奇妙な出来事に
遭遇したりしていたのでした。
自慢する程の能力があったワケでは無かったのですが、
夏時期の肝試し的な恐い話が盛り上がる時には、
会話の武器として体験談を話したりしていたのでした。
S子には当然、そういう話を聞かせていました。
「だってさぁ、期待してたんだもん」
「あのなぁ、見えないヤツは良いかもしれないケド、
下手に見えちゃったりしたら俺が恐いんだつうの」
「ええ~、どうしてもイヤ?」
「い・や・だ」
「どうしても?」
その日のS子は妙にしつこく了解を得ようとしました。
「じゃあ、Hが一緒に行くってOKしたら行ってやるよ」
「ホント!!」
Hは身長が180cmを超え、ラガーマンの様なワイルドな
体格を持った同じ剣道部の友人でした。
しかし、心霊モノが極端に苦手で、仲間内の呑み会などで
披露する私の恐怖体験なども聞くことを
非常に嫌がって話の途中で制止するような男でした。
私はHがOKするハズの無いことを確信していたので、
S子を制するためには丁度良いと思ってそう切り出したのです。
公衆電話のある場所まで戻り、剣道部のマネージャーでもあるS子が、
Hに電話をしました。
「あ、H先輩、お疲れ様です、S子です」
「おお、マネージャーか、どうした?」
「あの不躾なんですが、今からお時間空いてますか?」
「え?ああ、暇だけど」
「そうですか!あのBMWさんと一緒なんですけど」
「おお、なんだBMWちゃんと一緒なのか、遊びに来いよ」
「ええ、というか、中国人墓地って御存知ですよね」
「ああ、あのオッカネエところだろ」
「はい」
「それが何よ」
「あの、御一緒しませんか?中国人墓地まで」
「いいよ」
「やったあ!」
私は初めS子が演技をしているのだろうと疑いました。
あのHがOKするハズが無いと確信していたからです。
「ちょ、電話代われ!」
私はS子から受話器を受け取り、再確認しました。
「おい、H、ホントにOKしたのかよ」
「あ、え?いいよって言ったよ、BMWちゃんも行くんでしょ」
「馬鹿野郎ぉ、オメエがOKしたから行くことになっちゃったんだよ!」
「えええ?BMWちゃんが一緒に行くって言ったって聞いたから、つい・・・」
「あああ~、もう!俺車出すの嫌だから、オメエの車出せよ!」
「えええ?」
とにかく私達はHの車に乗り換え、旧道を中国人墓地へと向かいました。
ただ私は正確な場所を知らなかったので、上手くいけば到着しないんじゃないか?
という微かな期待みたいなものを抱いていました。
「なぁ、お前らちゃんとした場所知ってるの?」
私は助手席から残りの二人に聞いてみました。
「俺、この辺だっていうのは、随分前に昼間に通った時に聞いたなぁ」
暗くなり始めた旧道を運転する平方が自信なさ気に言いました。
「残ぁん念でしたぁ、ちゃあんと私が知っています!
この前の木曜、講義をサボって彼氏と来ちゃいました」
S子は後ろの席から身を乗り出してニコニコ笑って言いました。
「んだあ?行ったことあるんなら、もういいじゃねえかよ」
私はHに同意を求めました。
「いいえ、おにいちゃんとH先輩と行くところに意味があるんじゃない!」
この時点で、私の微かな望みは見事に断ち切られました。
ところが、です。
S子もHも、場所を知る二人が中国人墓地入り口への目印を
見落としたのです。
当時の北海道は都心部から離れる程、街灯の数が減り、
まして旧道の山道などでは星明かりと
自分の車のヘッドライトくらいしか、路を照らすものが無かったのです。
「あれ?おかしいなあ?」
「このへん?あ、違うなあ」
そんな言葉が少し続いた後、とうとう旧道の終点まで来てしまいました。
中国人墓地には行けなかったのです。
私は安心しました。
これで嫌な目に遭わなくても済むと思い、気分が緩みつい、
言ってしまったのです、余計な一言を。
「途中さあ、白い柱みたいなヤツがあったじゃん、左側に、
あれがそうだったんじゃねえの?」
「そう、それ!」
S子はHに目印を再確認し、私に戻り道で見えた場所で
指示するように強請って来ました。
私は何となく引き受けてしまいました。
そして後悔しながら、星でも眺めようと夜空を見上げました。
「!」
さっきまで見えていた星が、嘘のようにきれいさっぱり消えていました。
ただ真っ暗な空間が見えました。
私は昔から感じることのあった独特の嫌な感じを受け、
二人を、特にS子を説得しました。
もう、やめようと。
ところが、珍しく彼女は引き下がらず、途中までとか、
入り口までとか、いった条件を提示して来ました。
私はとうとう彼女の勢いに負け、入り口までで帰るという条件を承諾しました。
戻りの道すがら、S子とHは私の知らない中国人墓地にまつわる話を始めました。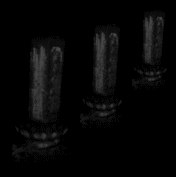
戦時中に強制連行させられた中国の人々の為の墓地であることや、
病や事故、中には強制労働の辛さに耐えかねて自殺などで
亡くなった方までが埋葬されていること、
旧道から脇に入った道のすぐ右手に墓地があり、そこがヤバイということ、
脇道を真っ直ぐ進むと終点にはロータリー状の広場があるので、
そこでUターンすれば何事もなく帰れるなど、
色々な話が車中で交わされました。
私が白い柱を見掛けた場所が近付いて来ました。
「多分・・・このカーブが終わったくらいの右側だよ」
私は諦めて正直に目印の場所を話しました。
その頃から、再び夜の空間が闇の様に見え始め、
独特な嫌な感じが私を支配していくのを体感していました。
「ホントだ、ここだよぉ」
「そう、ココ、ココ、おにいちゃん正直にありがとうね!」
私は自分だけが何かを感じるダケなら終点でUターンして
帰路につくまで我慢をして、市街に戻ってオチャを飲む時にでも、
フザケタ恐い話として話そうかと思っていました。
それは、脇道に入ってヤバイ場所を通過したあたりでした。
私の目に道いっぱいに広がった空気の壁の様なものが見えました。
それは固形であり液体でもあるかのように見えました。
私が目を凝らした瞬間、乗っていた車は当たり前のように
その不思議な物体に向かって進み、
衝突というか、のめり込んでしまった様になったのでした。
私の嫌な感覚は最高潮に達していました。
刹那、
「あぶねえええええええええええええ!!」
と叫んで、ステアリングを握るHの手を叩きました。
「うわ!」
驚いたHは急ブレーキを踏んだ様でしたが、既にその物体に
車の前半分がのめり込んでいました。
私は急に海や川などで溺れた時の様な感覚に襲われ、
呼吸困難になりました。
これから数分間、私は自分の息苦しさを払うのに夢中で、
周りを見る余裕はありませんでした。
以下、HとS子から聞いた数分間の状況です。
私が何かを叫んで手を叩かれた平方は、私から、
「逃げなきゃダメだ」
と言われたと思ったらしく、ギアをR(リバース)レンジに入れて
バックしようとしたそうです。
ところが、アクセルを踏んでも思った程下がらない。
一瞬にして恐怖に襲われたHは助けを求めて、私を見たそうです。
呼吸困難状態だった私は、喉と胸を押さえ涙まで流しながら、
痙攣の様な仕草をしていたそうです。
Hは益々恐くなり、アクセルを全開に踏んだそうです。
何度か鈍く反応がおこった後、車はアクセルにあわせて
バックしていったそうです。
S子は突然私が苦しみ始め、Hまでもがパニックになっていたので、
後部座席で独り恐怖に怯えながら、
目を閉じて耳を塞いでいたそうです。
何とか旧道に戻ることが出来た時、私の呼吸は段々と正常に戻って行きました。
涙が流れ、涎まで垂らしている自分に気がついたと同時に、
平方の必死の形相と、
「大丈夫かあ!」
という叫び声を認識しました。
「ああ、うん、もう大丈夫」
私の無事を確認すると、HはS子の安否を確かめました。
Hが後部座席にまわると、小さく固まって何か叫んでいる
彼女の姿がありました。
「おい、マネージャー、大丈夫か!」
S子の肩にそっと手を添えると、彼女は反動で飛び起き
天井で頭を打ってしまいました。
しばらくして、どうにか落ちついた私達は、市街へと逃げる様に帰りました。
時刻は既に深夜の2:00をまわっていました。
初めての恐怖体験をした二人の提案で、朝が来るまで
私の部屋で過ごそうということになり、
コンビニで買い物をして、私の部屋で先程の体験を恐々、話しました。
夜も明け、通勤通学の人々の時間が訪れたころ、二人は帰って行きました。
私は眠さの余りに恐怖感も講義も忘れ、そのまま寝てしまいました。
空腹で目が覚めたのは、夜の10時頃だったでしょうか、
つくりおきしてある総菜をレンジで温め直して
簡単な食事を取ると再び眠気に襲われ、また寝てしまいました。
夢の中で鳴っていた電話の呼び出し音が現実のモノであることに
気付いたのは、まだ暗い翌日の早朝でした。
「とにかく、すぐにウチに来てくれよ」
電話の主は、Hでした。
充分な睡眠明けにも関わらず、不快感を味わい過ぎたのか、
身体にはダルさが残っていました。
H宅について早々、彼の話が始まりました。
あの体験後、帰宅してHも眠気に勝てず深夜まで起きなかったそうです。
そして気が付くと、うつ伏せになって寝ている自分に気が付き、
寝返りをしようと思い、身体を起こそうとすると、
身体が痺れていることに気が付きました。
さほど気にせずもう一度寝ようとすると、頭の上で音がするのが聞こえました。
「何の音だ?」
Hは電灯を点けようとして起きあがりました。
・・・そして彼は見たのです、眼下で寝ている自分の姿を。
心臓が止まりそうに成ったそうです。
「幽体離脱」彼の頭の中で、その漢字四文字が強く
太い字となって何度も浮かんだのでした。
慌てて寝ている自分に戻ろうとすると、さっき気になった音が再び聞こえて来ました。
乾いた音でした、太鼓のようなリズムもある様に聞こえていました。
昨日、生まれて初めて不思議な恐怖体験をした平方でしたが、
これまでの情報から、とにかく早く寝ている自分に戻らなければ、
と思ったそうです。
寝ている自分に重なるようにして、今度は指先一本一本から
ゆっくりと動かしてみました。
意識のある自分の指と寝ている自分の指とが同じ動きを始めた時、
Hは頭の上の音が大きくなっているのに気が付きました。
そして、音に混じって人の声が聞こえる様になっていました。
流石に気になったHは動きを止め、話し声に耳を傾けました。
段々とはっきりと話し声が聞こえるように成った時、
彼は再び恐怖に全身を刺される様な感じを受けたそうです。
そう、話声はすべて中国語だったのです。
「うっ、」
恐さの余り、思わず声が出てしまいました。
すると、乾いた太鼓みたいな音は段々小さくなり、
部屋に静けさが戻ったように感じました。
途中だった身体を動かすことを慌てて始めると、
今度は思った通りに身体が動かせました。
そして今の出来事が夢で無かった証拠として、私に電話をしたのだそうです。
「そうか、嫌な体験しちゃったなあ」
私はどうしたものかと、一応、対策を考えました。
「また来るかなあ」
Hは不安そうに言いました。
「多分来るんじゃないかな、」
「ええ!?」
「俺も外国のってヤツは経験が無いから、何とも言えないけど、
俺のところに来ないでHんところに来たってこたあさあ、
何か意味が有るとおもうんだよなあ」
「意味?」
「いや、多分の話なんだけど」
「うん」
「でさぁ、もう手段としては、お前には何にもしてあげられないから、
来るな!とか言うしか無いんじゃないかなあ、」
「えええええ?」
「何なら今晩一緒にいてもいいけど、俺がいるときだけ
来ないって可能性もあるからなあ、」
結局、その日の夜はHが独りで対応してみるということに成りました。
私も寝ずにHからの連絡を待つという形をとることにしました。
深夜も二時をまわった頃だったそうです。
果たして、その日も彼らはやって来ました。
合図の様に乾いた太鼓が鳴り始め、彼らの声が聞こえて来ました。
Hは恐怖心でいっぱいで目を開けることは出来ませんでしたが、
彼らの言葉を理解しようと、少し努力をしました。
しかし、やはり全く解らなかったので出来る限り穏やかに、こう言いました。
「ごめんなさい、何を言ってるのか解らないし、俺は何にもしてあげられない」
トン、と背中を圧された感触がありました。
次の瞬間、Hは全身の力が抜けてしまい、そのまま寝てしまったそうです。
翌日から、彼らが訪問してくることはありませんでした。
その後、HからもS子からも、この件に関連した
出来事があったとの話はありません。
しかし、私は大学を卒業し広告の世界に身を置くことになり、
夏場の怪談などの企画にこの話を使おうとしたのですが、
パソコンがいきなり壊れたり、原因不明の頭痛に襲われたりして、
最期までこの話を書けたことが、ありませんでした。
今回こういう風に最期まで書けたということは、
きっと彼らの許しがあったということなんだと思います。
結局この出来事の真相は不明ですが、面白半分に聖域などを犯してはならないという
戒めだったのではなかったのでしょうか。
フィクションでは無い為、この話には具体的なオチがありません。
本当にあった怖い話なのですから。